こんにちは。えっくすはっかーです。
今日、説明するのは論語!
論語は言わずと知れた中国の古典名書。四十不惑、四十にして惑わず、という表現は論語というイメージが強いですが、切磋琢磨、温故知新、過ぎたるは猶及ばざるが如し、、、、と、日本人の文化に根付いている言葉がたくさんあります。
そんな論語ってどんな書なのだろう、孔子ってどんなことを考えてたんだろう、ということを改めて勉強してみようと思いました。
今回参考にした本はこちら
まんがで勉強するのは、実は結構オススメ。とくにかたい内容の本だったりすると、ストレスなく頭に入ってくるのでいいですね。
この本では、アイドルオタク男子高校生である湊(みなと)が、挫折を乗り越えて音楽部に入り仲間と協力をしてコンクール優勝を目指す、というストーリの中で論語を学んでいくことができます。
今回のブログでは、この中で出てくる論語の言葉のうち、響いたもの、言いたくなったものをピックアップしてお伝えします。
- 当ブログマッチ度No.1!「これを楽しむ者に如かず」
- 言いたくなる表現No.1!「今女(なんじ)は画(かぎ)れり」
- 孔子の心が詰まった言葉「人を愛す」
- まとめ「習えば、相い遠し」「また説(よろこ)ばしからずや」
当ブログマッチ度No.1!「これを楽しむ者に如かず」
もう少し長く引用すると
「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。」
訳『学ぶことにおいて、知っているだけでは好むには及ばない。また、学問を好む者は、学問を楽しむ者には及ばない。』
学ぶことを「知る」「好む」「楽しむ」という三段階に分けて比較しています。
知るために学ぶのではなく、好きだから学ぶというレベルでもなく、学ぶことが楽しくて仕方がないという状態が最高!
このブログも「より楽しく」ということを目指していますが、論語にもバッチリリンクしていたんですね!
言いたくなる表現No.1!「今女(なんじ)は画(かぎ)れり」
元の文は
「冉求(ぜんきゅう)が曰わく、子の道を説(よろこ)ばざるには非ず、力足らざればなり。子曰く、力足らざる者は中道にして廃す。今女(なんじ)は画(かぎ)れり。」
訳『冉求(ぜんきゅう)という弟子が「先生の道を学ぶことを幸せに思っていますが、私の力が足りず、なかなか身に付けるに至りません。」と言うと、先生はこう言った。「本当に力が足りない者は、やれるだけやって途中で力尽きてやめることになる。お前はまだ全力を出しておらず、自分で自分の限界を設定してやらない言い訳をしている。」』
なかなかに厳しいお言葉。
でもこれは、無限の可能性があるんだから簡単に自分の天井を決めるな、という意味のように思います。
無限の可能性を信じて成長していきましょう!
諦めていたり、自分を過小評価していたりする人に言いたいですね。
「今女(なんじ)は画(かぎ)れり!」
孔子の心が詰まった言葉「人を愛す」
前後の文は
「樊遅(はんち)、仁を問う。子曰わく、人を愛す。知を問う。子曰わく、人を知る。」
訳『樊遅(はんち)という弟子が「仁とは何でしょうか」と聞くと、先生は「人を愛することだ」と答えた。「知とは何でしょうか」と聞くと先生は「人を知ることだ」と答えた。』
孔子が大事にしていた3つの徳、「知」「仁」「勇」。「知」とはいろんな物事がよくわかるということ。「勇」とは勇気のこと。そして、仁とは何かと聞かれたときの答えが愛であると。
論語とは、孔子の教えであり、儒教の中心となる教えです。
学ぶことや人生感について、結構厳しいことも書いていますが、一番大事にしているのが「仁」。その「仁」というのは人を愛することである、という一説。
少し論語のイメージが変わりますね。
まとめ「習えば、相い遠し」「また説(よろこ)ばしからずや」
「性、相い近し。習えば、相い遠し」
人間は生まれたときは互いに似ているけれど、学ぶか学ばないかによって違いが出てくる。
「学びて時にこれを習う、亦(ま)た説(よろこ)ばしからずや」
学ぶことは楽しいことだし、またそれをおさらいするのも楽しい。
これからも一緒に楽しく学んでいきましょう!




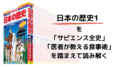
コメント