こんにちは。えっくすはっかーです。
今回読んでみたのは、渋沢栄一さんの「論語と算盤」。
渋沢栄一といえば、2024年度に刷新される新紙幣の一万円札の図柄になることで話題になりました。
今まであまり気にかけたことはなかったのですが、中田敦彦さんのYoutube大学でも取り上げられたこともあり、少し気になったので読んでみました。
今回は、簡単なまとめと感想を書いてみます。
渋沢栄一とはどんな人か
「日本資本主義の父」「実業界の父」ともいわれる渋沢栄一とは、どのような人物なのか。
超簡単にまとめてみます。
- 1840年、今の埼玉県深谷市の豪農に生まれる
- 尊王攘夷活動の後、一橋慶喜に仕える
- フランスのパリ万博などを目的にヨーロッパを訪れているときに江戸時代が終わる
- 日本に戻ったのち、大蔵省にて租税制度の改正、貨幣制度改革など、さまざまなルール作りに携わる
- 実業界に活動の場を移し、数多くの企業、教育機関の設立に携わる
幕末から明治という激動の時代に生き、活躍したことが読み取れますが、驚くべきは設立に携わったといわれる企業の数とその内容。
今のみずほ銀行、JR、帝国ホテル、東京ガス、王子製紙、サッポロビールなど、481社の会社設立に関わり、それ以外に500以上の慈善事業にも関わったといいます。
日本商工会議所や東京証券取引所の設立、一橋大学、早稲田大学、同志社大学、日本女子大学などの創設、明治神宮の造成にも中心人物として関わっています。
1人の人間でここまで主要な会社、組織に関わることができるのかと驚くばかりです笑
そんな渋沢栄一がどのようなことを考え、どのような思想を大事にしていたのかがうかがえるのが「論語と算盤」です。
精神と商売
武士と町人・百姓では考え方や教育についても大きく異なっていた江戸時代。武士は、武士道にみられるような精神に重きをおき、「武士は食わねど高楊枝」とあるように、数字や商売についてはあまり重視をしていなかったようです。
逆に、町人や百姓は精神のあり方についてはあまり重きは置かれず、教育もあまり行きわたってはいませんでした。
そんな中で、渋沢栄一は精神の在り方も、商売のことも、どちらも重要になるということを見抜いていたようです。
この考えが「論語と算盤」というタイトルに繋がっています。
国家のため、社会全体のため
「論語と算盤」では、全体を通して『国家のため』を思う渋沢栄一の思想が伝わってきます。
1873年6月11日に渋沢栄一は日本で最初の銀行、「第一国立銀行」(現在のみずほ銀行)を設立しましたが、そのときにも根底にあったのは社会のため、世の中のためという考え方。
「どこかの蔵の中や、個々人のふところの中にあるお金を、銀行に集めて実業のために回したい。それが日本のためになる」という考えが根底にありました。
渋沢栄一が財閥を作らず、数多くの会社や教育機関、慈善事業団体の設立に奔走したのも、個人の利益ではなく社会全体のことを思ってのことでした。
「一個人の利益になる仕事よりも、多くの人や社会全体の利益になる仕事をすべきだ」という思想が常にあります。
さいごに ~感想~
私もそうですが、普段何気なく生きていると、自分自身のことで精いっぱいになります。
そんなとき、この本を読むと自然と視線が上がるかもしれません。
ちなみに、個人にも関わるところでは渋沢栄一は
- 蟹穴主義(自分の身の丈を知り、身の丈に合った仕事をする」
- 「お金はよく集めて、よく使う」べき
- 「欲望と道理のバランス」を取ることが大事
ということも言っています。
実際に読んでみると、渋沢栄一の考え方、熱量がなんとなく伝わってきますので、是非一度読んでみてください。
「国家のため」と考えるのはなかなか難しところがありますが、私も視座を高く持ち、社会のために自分の能力を発揮できるように心がけていこうと思います。




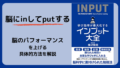
コメント