こんにちは。
x_hackerです。
今日は効率よく勉強をするための教材の選び方について。

子どものころは受験勉強、大人になってからもいろいろな資格試験のための勉強をしている方も多いと思います。
勉強において非常に大事なのは①目標設定とスケジュール管理、②教材の選定、③勉強方法、の3点。今日はその中でも教材の選定についてお伝えします。
- 超まとめ
- ゴール設定を間違えるな
- 基本セットは「参考書+過去問」の2冊。
- 参考書は薄さと中を見たときのフィーリングで選ぼう
- 問題集(過去問集)は解説の読みやすさと充実度で選ぼう
- 選んだ参考書と問題集を最後まで信じ抜け
ちなみに、③の勉強方法についてはこちらも是非
東大にも合格できる!?効率化を突き詰めた最強の勉強法
超まとめ
教材は、薄くて見やすくてフィーリングが合うものを選べ。
ゴール設定を間違えるな
勉強をする理由や目的は人によって異なります。
ここでは、受験勉強、特に資格試験の受験勉強についてのお話をさせていただきます。
資格試験の勉強のゴールはズバリ「合格すること」。
そこに向かって最短ルートを取れるような教材を選びましょう。
教材を選ぶときに、とにかく情報量の多い参考書にしなければ不安、というタイプの方も多いと思いますが、それはナンセンス。
資格試験では100点を取る必要はないのです。
合格点を取ることができれば、いくらかは間違ってもオッケー。この考えがまず大事。
基本セットは「参考書+過去問」の2冊。
「いっぱい勉強しないと不安だからいっぱい問題集をやっておこう」と思ってしまうかもしれませんが、勉強の基本は「必要最低量の問題を反復して覚えきること」と理解しましょう。
以前の記事に書いた通り、勉強した内容を覚えるためには何回も反復することが重要です。
何回も反復しようとしているのにたくさんの問題集を買ってしまうと、時間がいくらあっても足りません。
厳選した参考書と問題集をそれぞれ1冊買うようにしましょう。
そしてたいていの資格試験では厳選した問題集にあたるものは過去問集です。
過去問は5年分程度のものがよいでしょう。
何回も反復したいので、基勉強セットは始めの知識習得のための参考書1冊と過去問集1冊の計2冊が基本。
難易度の高い試験だと、過去問では対応できないケースもありますので、その場合は過去問ではない問題集等にしましょう。
参考書は薄さと中を見たときのフィーリングで選ぼう
内容量が少なく、薄い参考書がいい
1つの資格試験の参考書でも、薄いものから厚いもの、何冊かに分かれているものまでいろいろあります。
まず分量に関しては「できるだけ薄いもの(内容量が少ないもの)」を選びましょう。
始めにお伝えしたように、資格試験勉強の目的は合格すること。
60点が合格ラインの試験であれば、40点分は間違っていいのです。
本屋に普通に売っているものはどんなに薄い参考書でも合格点に届く程度の内容は載っていると考えられますので、一番薄いものでよいと思います。
逆に、その薄い参考書の内容は完璧に覚えよう、という意識が大事。
100点分をぼんやり勉強して60点を取るより、60点分を完璧に覚えて60点を取るような勉強をしましょう。
90点を100点にする勉強は大変だが、50点を60点にする勉強はそこまで大変ではない、というのは感覚的には理解できると思います。
100点満点分の参考書を購入すると分量が膨大になり、習得に非常に時間がかかるうえに結局は完璧に覚えることができません。
それならば、少しくらい対応できない領域があったとしても60点分が載っている参考書を完璧にする方が圧倒的に効率よく勉強できます。
参考書は、「何でも調べられる参考書」ではなく、「合格に最低限必要な分だけ載っている参考書」という意識で選びましょう。仮にその参考書に載っていないような問題がでたら「この問題は捨て問題だな」と思いましょう。
そうすることで、効率よく学べるものと、学ぶと時間効率が悪いもの(異常に難しい、出題頻度が極めて低いなど)を簡単に見分けることができるようになります。
見やすくフィーリングの合う参考書を選ぶ理由
次に参考書の中身や書き方、構成についての部分での選び方をお伝えします。
これは本当にズバリ「フィーリング」で選んでOKです。
書店でパラパラと中を開いてみてみて、「これは何となく読みやすそう」という選び方で大丈夫。
この教材を超長時間何度も反復して見るため、最もストレスの少ないものを選んでください。
カラーが好きであればカラーで、漫画が載っていると読みやすいというのであれば漫画付きのものでかまいません。
強いて言えば、カラーで漫画やイラスト付きの方が印象に残りやすいので覚えやすいかもしれませんが、モノクロ好きであればモノクロで全然大丈夫です。
問題集(過去問集)は解説の読みやすさと充実度で選ぼう
問題部分は分野別ではなく年度別のもの
過去問集の場合、問題自体はどの過去問集でも同じですが、問題の並びが異なるものがあります。
どう違うかというと、分野別にまとめなおしているものと年度別に並べているだけのもの。
年度別の方を選びましょう。効率の良い勉強のためには全分野横断的に反復するのが効果的だからです。
解説が読みやすく、充実しているものを選ぼう
問題は同じでも、解説部分は本によって結構異なります。解説が簡単に書かれているものもあれば、詳細が載っているもの、参考書と連動しているものなどがあります。
過去問は解説で勉強するといっても過言ではないので、解説が充実しているものを選びましょう。ただし、参考書選びのときと同じで、読みやすいもの(見やすいもの)というのも大事です。
選んだ参考書と問題集を最後まで信じ抜け
参考書や問題集は、購入するまではたくさん悩んで選べばいいと思いますが、一度選んだ参考書と問題集は受験のその日まで信じ抜きましょう。
やっぱり違う参考書にしよう、なんてことをやっていると、始めに選んだ参考書の内容を覚えきることなんてできません。
自分で選んだ本を信じ、少なくとも5回、できれば10回繰り返して確認し、完璧に覚えることができれば、たいていの試験には合格できるでしょう。
具体的な勉強方法はこちらも参考にしてみてください。
東大にも合格できる!?効率化を突き詰めた最強の勉強法


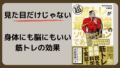
コメント